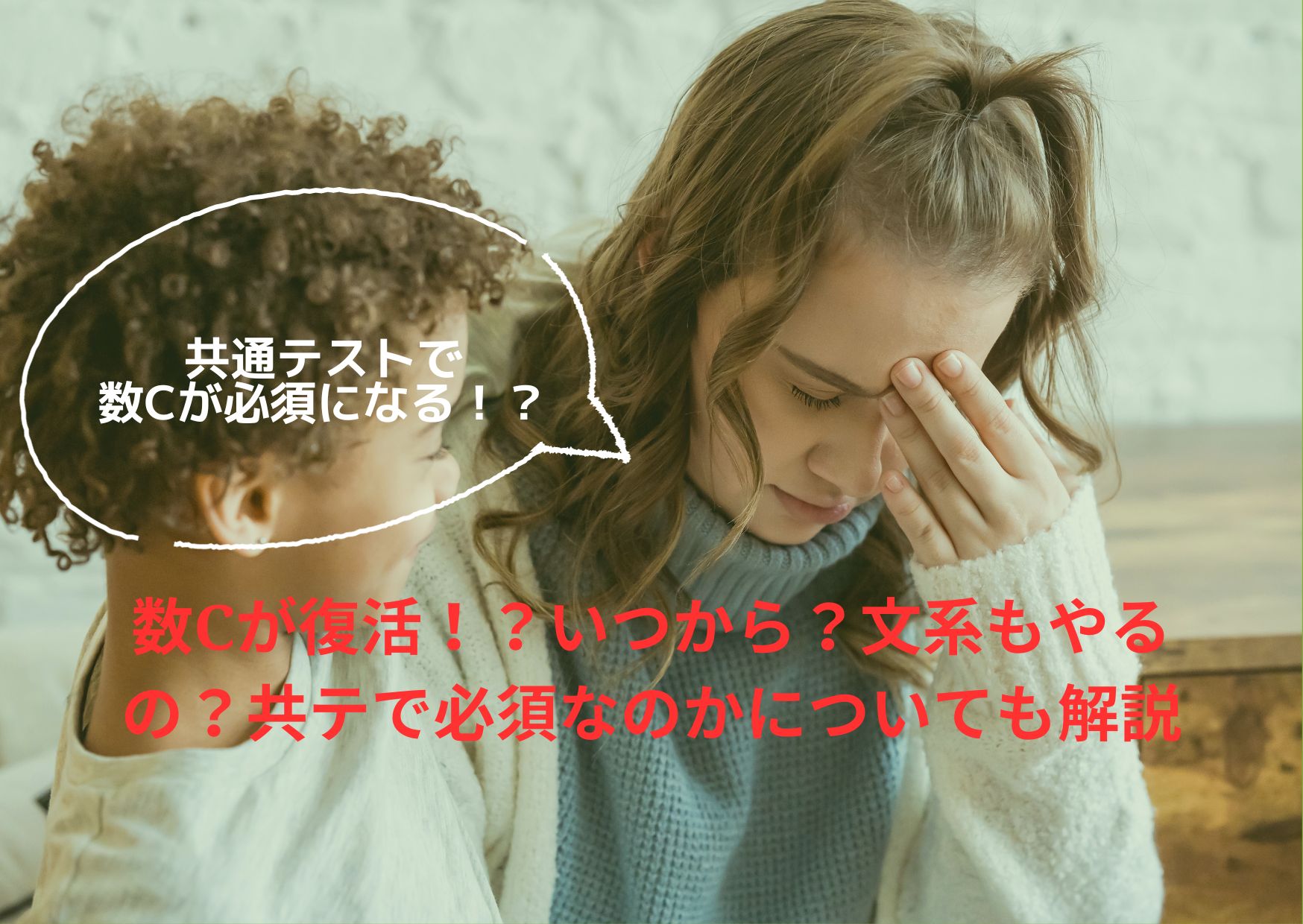数学C(数C)は高校の数学科目の一つで、数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲに続く科目です。
2012年度から2021年度までの間、他の科目との統合により一時的に廃止されましたが、2022年度から新しい学習指導要領により復活しました。
今回は、数学C(数C)が復活したのは本当なのか、いつから始まるのか?そして数Cで学ぶ範囲や内容についても解説します。
文系だから関係ない…と思っている方、理系の農学部、獣医学部、薬学部志望の方も必見ですよ。
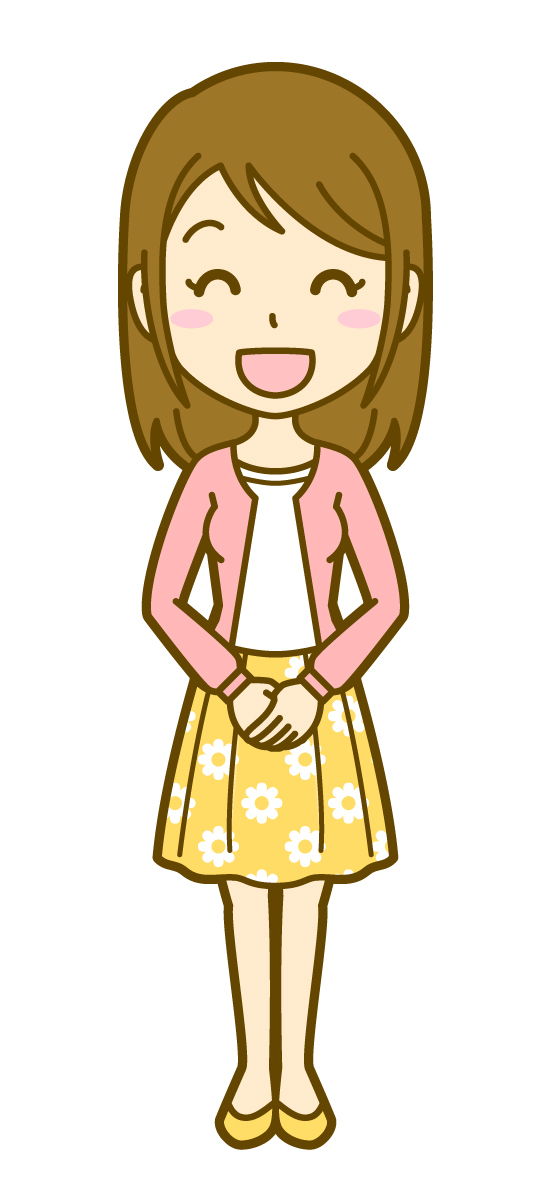
2025年1月に実施される共通テストから数Cが入り、1問必須になり、文系の受験生はベクトルを選択するしか方法がありません。あなたに合う方法で教えてもらうのなら、マンツーがベストです。でも、いきなり家庭教師をつけることや、マンツーマン塾に入塾するのは塾代も高額なので失敗したら…と思うと不安かもしれません。まずはオンラインのマンツーマン無料体験指導を受けて、あなたに合った数学の対策を教えてもらう方法もあります。今なら完全無料で体験授業を受けられますよ。
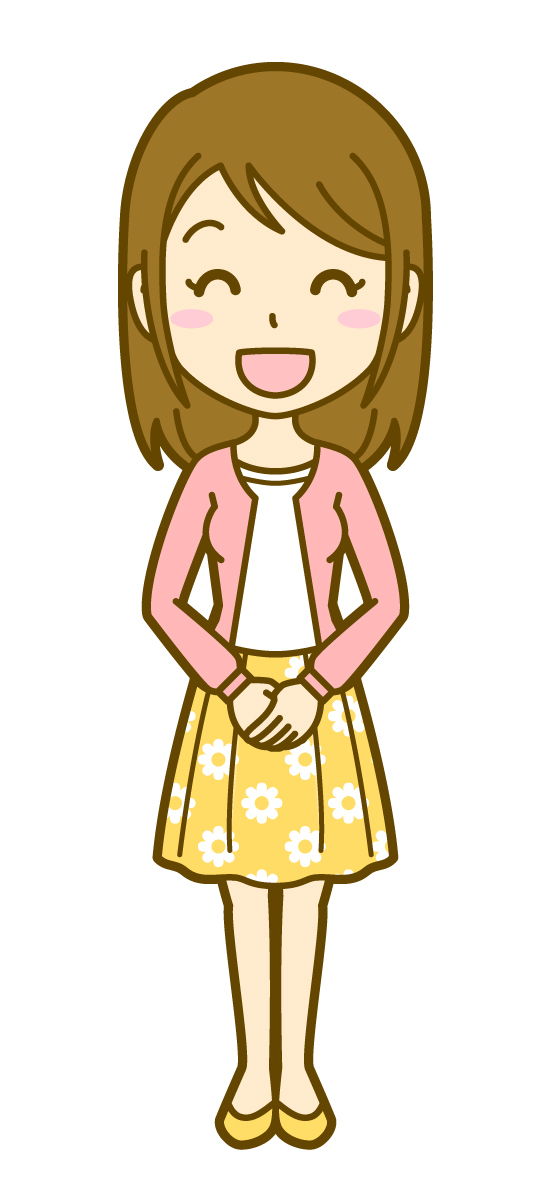
オンライン指導は不安…対面式で教えてもらいたいのなら、家庭教師という選択肢があります。
家庭教師センターの一括資料請求を申込めば、今住んでいる地域の家庭教師会社の資料をすべて無料で送ってもらえます。
その中から、数C含めた数学の対策をしてくれる家庭教師を見つけることができますよ。
資料請求までの流れは、たったの2分です。簡単な質問に答えるだけでOKですよ。
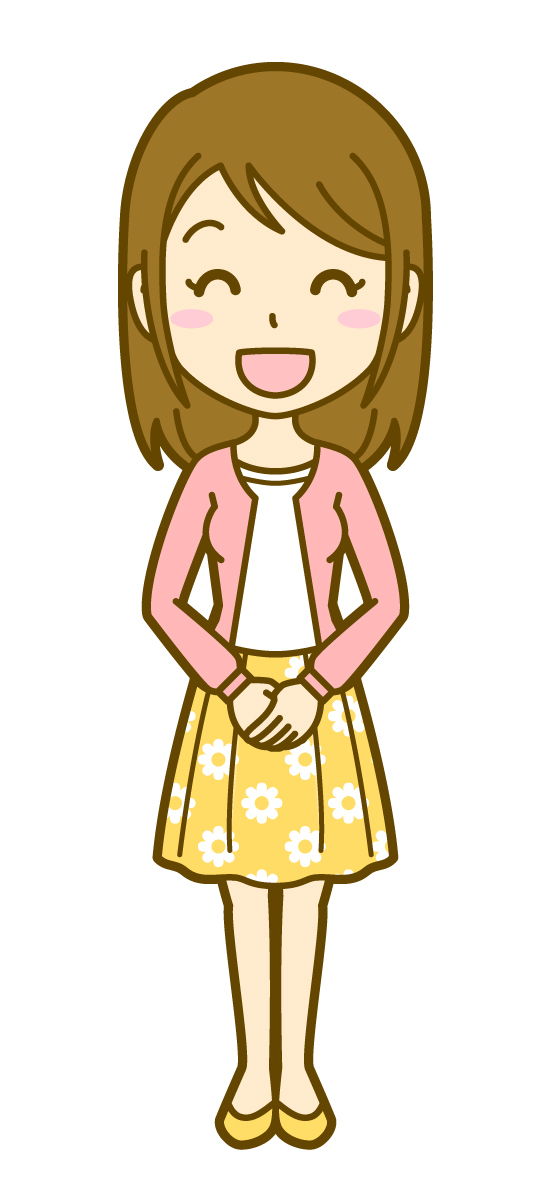
資料請求よりも、無料体験授業を受けてみたいというのなら、
地域と学年から無料の体験指導が受けられる家庭教師会社が検索できますよ。
数Cが復活したというのは本当か?
2012年度から2021年度までの間、他の科目との統合により一時的に廃止されていた数学C(数C)。
2022年度から新しい学習指導要領により復活するとか、復活したと言われていますが、正確には一部が復活したという方が正しいでしょう。
実際に、新しい指導要領では、数学Cは「ベクトル」「複素数平面」「式と曲線」「数学的な表現の工夫」を扱う科目となっています。
つまり、これまでの数学B(数B)の範囲であった「ベクトル」、数学Ⅲ(数Ⅲ)の範囲であった「複素数平面」「式と曲線」、「数学的な表現の工夫」では離散グラフや行列を扱う内容となっています。
数Cが復活したと言われる理由には、2012年度から2021年度までの間、他の科目との統合により一時的に廃止されていた「行列」が高校数学に再び戻ってきたこともあります。
数Cはいつから大学入試の範囲になるのか?
数Cは、2022年4月に高校1年生になった生徒たちから授業で始まるので、2025年度の入試から範囲に入ってきます。
高校によっては、2023年9月現在、教科書が配布され、高校2年生の数学の授業で始まる高校もあります。
超進学校や、中高一貫校でない限りは、数Ⅰ、数A、数Ⅱ、数B、を履修してから、数Cに入るので、高校3年生になってからスタートするのが一般的でしょう。
個人的に言わせてもらうと、高校3年生の後期から開始とか言っている高校もあるようですが、大学受験は対応できません、個々で対応して!と言っていると受け取るのが正解です。
だとしても、文系だから関係ない~と思っている方々は要注意です。
というのも、共通テストには数Cが入ることが確定しているため、国公立の個別入試に数Cが入るという可能性がゼロではなくなってきているのです。
⇒⇒オンライン家庭教師の無料体験授業で、あなたに合う数学対策のアドバイスを受けてみる
数Cは文系でも必須な生徒がたくさんいます
数Cは文系であっても、大学受験に必要かどうかによって必須なのかも変わってきます。
まずは、数Cの範囲、学ぶ内容をみていきましょう。
数Cの範囲、学ぶ内容を紹介
数学C科目は、高校生が大学入試に向けて必要な数学的スキルを磨くための重要な科目です。
この科目は、ベクトル、式と曲線、複素数平面などの数学的概念を深く理解し、微積分や確率統計などの実用的な問題を解決する能力を育むことを目的としています。
繰り返しになりますが、これまでの数学B(数B)の範囲であった「ベクトル」、数学Ⅲ(数Ⅲ)の範囲であった「複素数平面」「式と曲線」、「数学的な表現の工夫」では離散グラフや行列を扱う内容となっているのです。
なので、当然、現行の数ⅡBがヤバい、数Ⅲがヤバい、といっている人たちからすると、もう、一人では太刀打ちできないし、短期間でどうかできるような科目ではなく、相当ヤバい科目と言えます。
⇒⇒オンライン家庭教師の無料体験授業で、あなたに合う数学対策のアドバイスを受けてみる
共通テストで数Cが必須になるのは本当!
結論からいうと、2025年1月実施の共通テストから数Cが入ってきます。
まず、共通テストをみていくと、次のように発表されています。
2021年3月24日に大学入試センターより発表された「平成30年告示高等学校学習指導要領に対応した令和7年度大学入学共通テストからの出題教科・科目について」によると、共通テストは以下のように変更になります。なお、今後の検討によっては、さらに変更になる可能性もあります。
新課程の共通テストでは、『数学I・数学A』、『数学I』、『数学II・数学B・数学C』の3科目が出題される。
つまり、共通テストで数学2科目必要で、『数学II・数学B・数学C』を選択する場合は、文系であっても数Cをやらなくてはなりません。
このあたりは、国公立の各大学が、共通テストの数学で、どの科目を課すのかによります。
といっても、現実的には、多くの高校では、文系の生徒は数Cに関しては「ベクトル」だけ履修することになりそうです。
もし、受験したい国公立大学で、共通テストは数学2科目必要で、『数学II・数学B・数学C』を選択するとなっているのなら、早めの対策が必要ですよ。
⇒⇒オンライン家庭教師の無料体験授業で、あなたに合う数学対策のアドバイスを受けてみる
個別試験は数Cが入るのか?
大学入試センターが共通テストで「数学C」を課すことを正式に発表したことにより、文系の個別試験や、理系でも農学部、獣医学部、薬学部系の出題範囲に影響がでてくる可能性は高いです。
例えば、文系学部であっても「ベクトル」を個別試験の出題範囲に含めるとか、数IIIを出題範囲から除外していた理系の農学部、獣医学部、薬学部系でも、これまで数Ⅲの範囲であった「複素数平面」「式と曲線」が出題範囲に含まれる可能性もあるでしょう。
もし、受験したい国公立大学の個別試験で「数学C」を範囲に入れるのであれば、早めの対策が必要ですよ。
⇒⇒オンライン家庭教師の無料体験授業で、あなたに合う数学対策のアドバイスを受けてみる
まとめ
数Cが復活した…と言われていますが、廃止されていた数Cが完全に戻ってきたというよりは、数Cの範囲の「行列」が高校数学に再び戻ってきたということでした。
2025年1月実施の共通テストから数Cが範囲に入ってくるので、共通テストの数学で『数学II・数学B・数学C』を選択する場合は、文系であろうと「数学C」特にベクトルをやらなければなりません。
また、これまでは数Ⅲが除外されていた理系の農学部、獣医学部や薬学部でも、共通テストの数学の範囲に数Cが入ることになったことで、個別試験の範囲が増える可能性も出てきました。
大学受験に数Cが必要なら、早めに対策をしておきましょう。
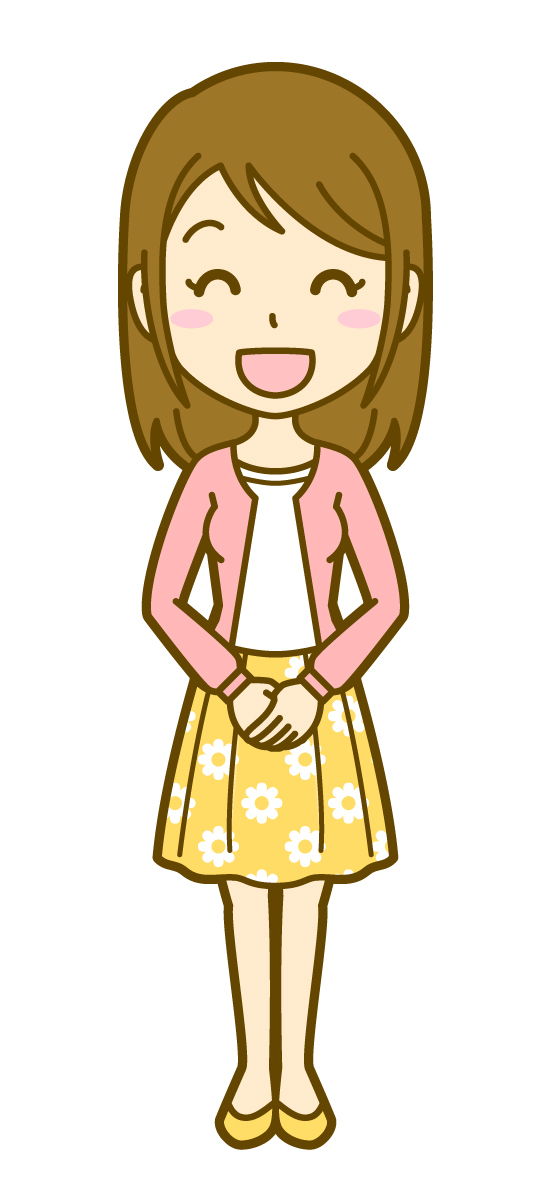
2025年1月に実施される共通テストから数Cが入り、1問必須になり、文系の受験生はベクトルを選択するしか方法がありません。あなたに合う方法で教えてもらうのなら、マンツーがベストです。でも、いきなり家庭教師をつけることや、マンツーマン塾に入塾するのは塾代も高額なので失敗したら…と思うと不安かもしれません。まずはオンラインのマンツーマン無料体験指導を受けて、あなたに合った数学の対策を教えてもらう方法もあります。今なら完全無料で体験授業を受けられますよ。
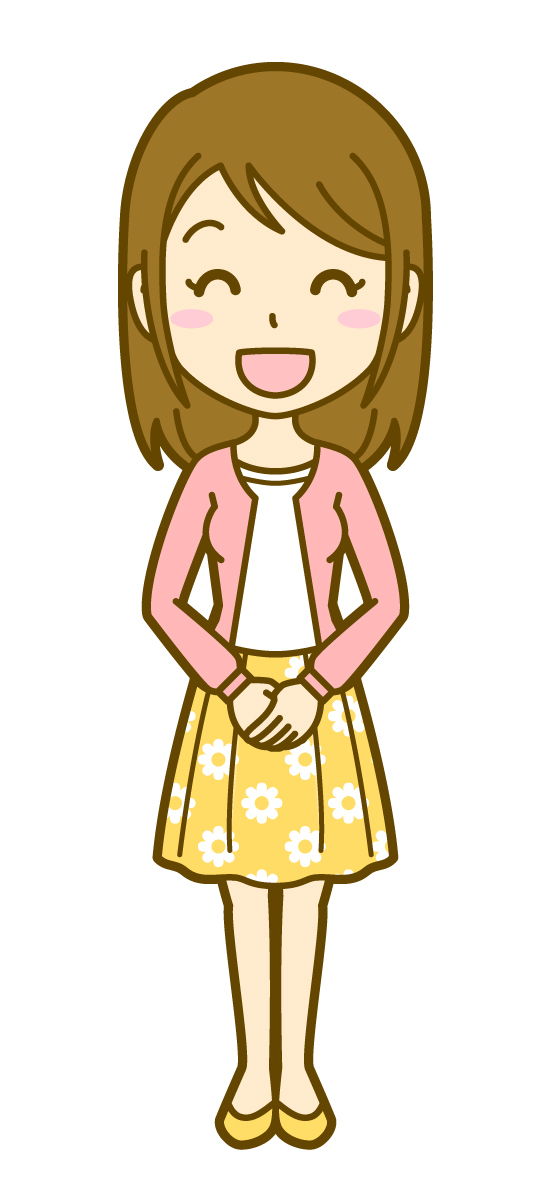
オンライン指導は不安…対面式で教えてもらいたいのなら、家庭教師という選択肢があります。
家庭教師センターの一括資料請求を申込めば、今住んでいる地域の家庭教師会社の資料をすべて無料で送ってもらえます。
その中から、数C含めた数学の対策をしてくれる家庭教師を見つけることができますよ。
資料請求までの流れは、たったの2分です。簡単な質問に答えるだけでOKですよ。
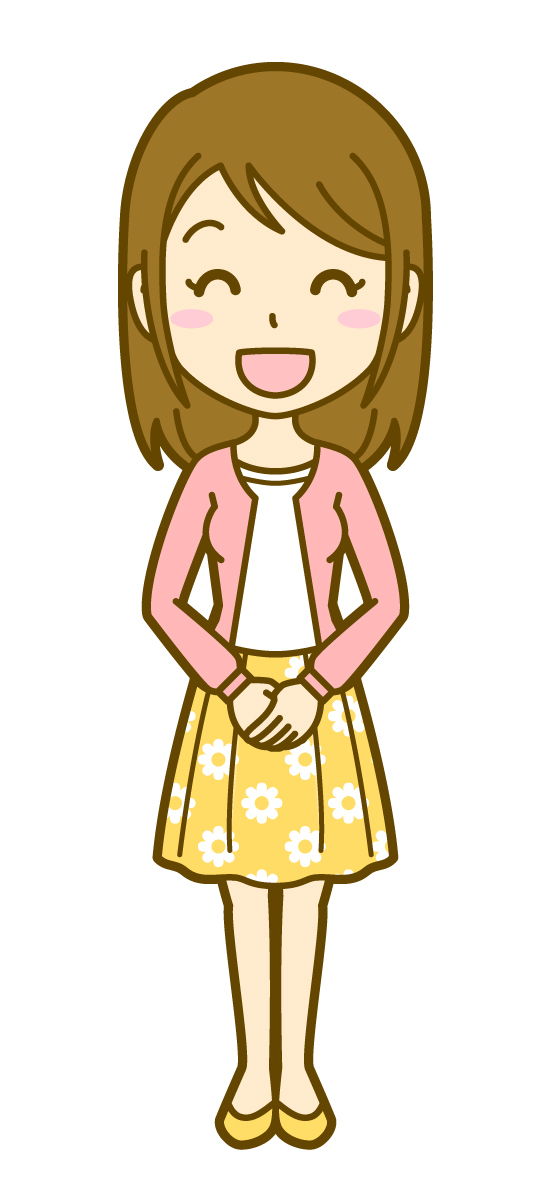
資料請求よりも、無料体験授業を受けてみたいというのなら、
地域と学年から無料の体験指導が受けられる家庭教師会社が検索できますよ。