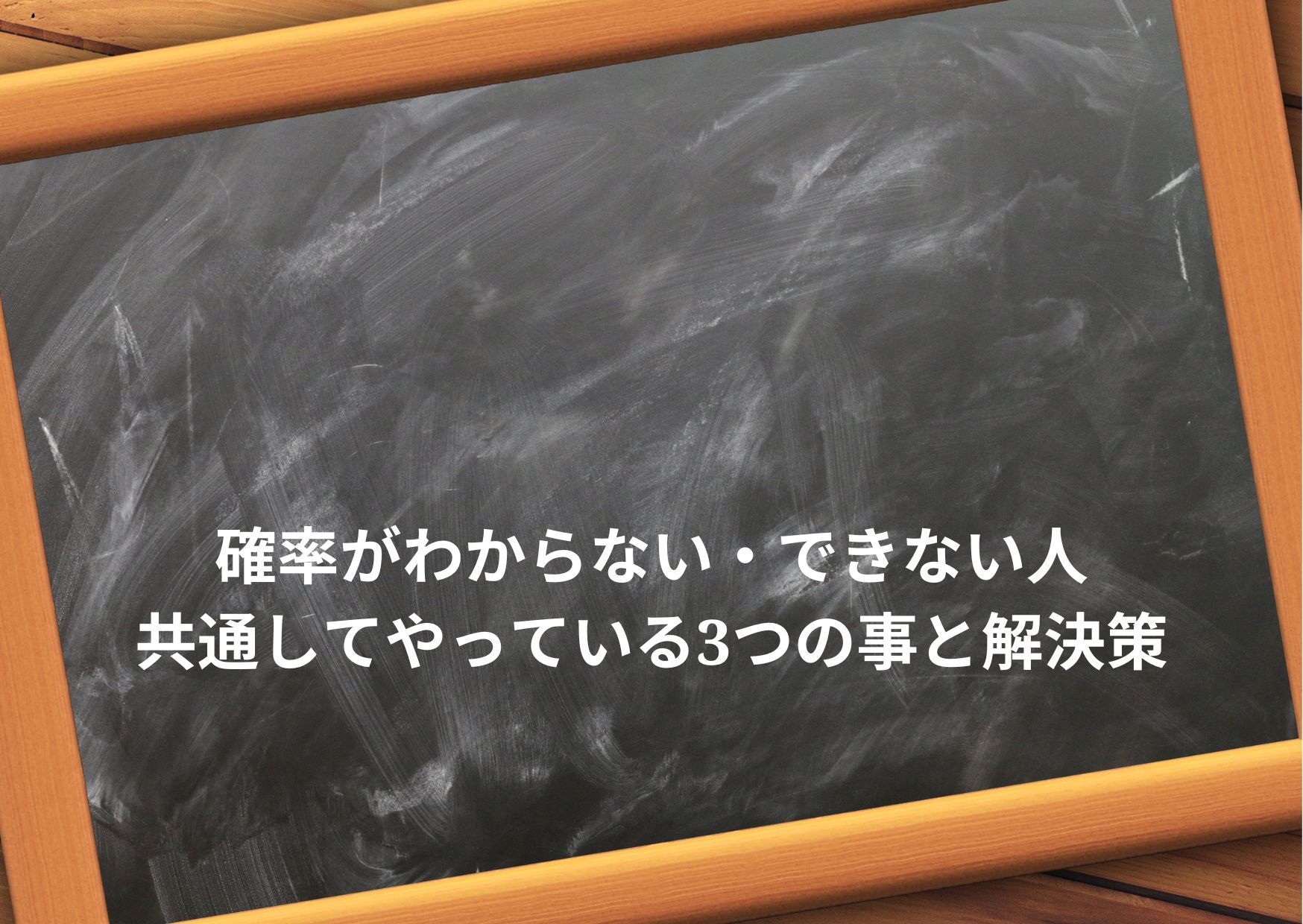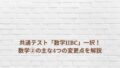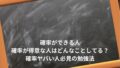確率がわからない、確率ができないという高校生、実は非常に多いのです。
数学の他の分野は点数が取れるのに、確率はダメ‥という人もいるほど。実態は想像以上に多いんです。
2024年の共通テストまでは、確率が嫌!というのなら、確率を避けて受験することもできました。
しかし、2025年以降の共通テストはいよいよ確率がほぼ必須となるため、避けることができなくなりました。
私の長年の指導経験から感じていることは、確率を苦手とする人たちには、共通している行動パターンがあります。
この記事では、確率がわからない、確率ができない人が共通してやりがちな3つのことを掘り下げ、それらを克服するためのアプローチを紹介します。
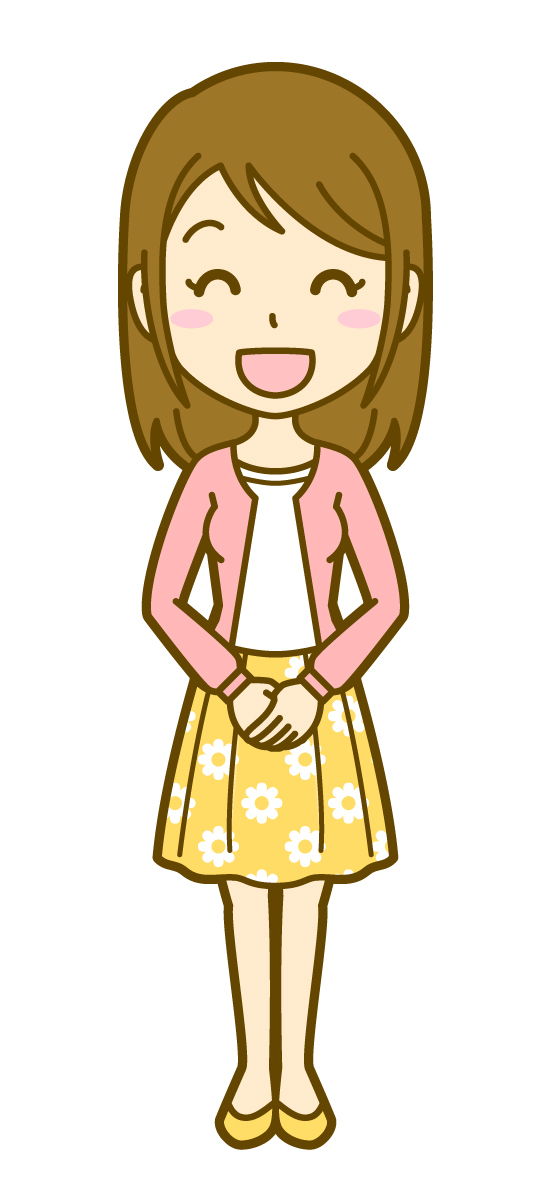
2025年の共通テストから確率はほぼ必須確定です。確率がわからなすぎ、確率ができなさすぎでどうしたらいいのかわからないのなら、マンツーマンでやり方を教えてもらうのがベストです。でも、いきなり家庭教師をつけることや、マンツーマン塾に入塾するのは塾代も高額なので失敗したら…と思うと不安かもしれません。まずはオンラインのマンツーマン無料体験指導を受けて、あなたに合った対策を教えてもらう方法もあります。今なら完全無料で体験授業を受けられますよ。
確率がわからない・できない人がみんなやってる3つのこと
多くの高校生を指導する中で、確率を理解するのが苦手な人には共通点があると日々感じています。
ここからは、確率がわからない、確率ができない人が共通して行っている3つのことを具体的にあげていきます。
公式に頼っている
確率を苦手と感じる学生に共通して見られる傾向が「公式頼り」です。
PとCの違いもよくわからないまま、一か八かで、これはPだろ、あれ、答えが違った、Cなのか‥とかやっていませんか?
確かに、CやPのような公式を暗記することにも意味がありますが、確率の場合、公式が全ての問題を解決するわけではありません。
つまり、すべての問題が公式によって解決されると思い込むことはリスクが伴います。
公式に頼ることをやめるためには、意図的に公式を使わない方法を試すことです。
【関連記事】確率ができる人・確率が得意な人は何してる?確率ヤバい人必見の勉強法
問題を具体的な状況に置き換えない
確率に限らず、数学の問題が解けない、特に初見の問題が解けない人は、問題を解く際に抽象的なまま考えがちです。
抽象的に問題を解くことが可能な場合もありますが、確率の場合は、問題をより具体的な状況に置き換えて考えることで解く糸口が見つかるケースが多いです。
つまり、確率の場合は具体的な視点から問題を考えていく中で、多くの場合「ああ、そういうことか」という理解にいたるのです。
【関連記事】確率ができる人・確率が得意な人は何してる?確率ヤバい人必見の勉強法
演習が足りていない
確率に限らず、できないという場合はそもそも演習が足りていないのです。
できないとか、わからないといった、苦手意識を持つ人は、無意識のうちに練習量を減らしてしまうことがあります。
特に確率の場合、方程式や関数と違って、中学2年生で初めて数学で触れ、高校1年生で本格的に習います。
少ない人では、この習っている間の課題程度しかやっていないという強者もいます。
2025年以降の共通テストを受験する学年となると、数Bの「統計的な推測」が必須となり、この分野でも確率は必須で、いよいよ大学受験から確率を切り離せなくなる世代です。
演習量が足りない理由だけなら、意図的に練習量を増やすことで苦手を克服できますので、確率専用の練習問題集の活用が良いでしょう。
【関連記事】確率ができる人・確率が得意な人は何してる?確率ヤバい人必見の勉強法
確率の問題を攻略する方法
ここからは、確率問題を解くうえで、どんなことを意識したら、確率ができるようになるのか、具体的にあげていきますので参考にしてみてください。
具体的な数値を使って考える
前述の通り、確率問題を具体的に捉えることで解きやすくなることが多いです。
具体的に考える際には、「3」や「5」といった具体的な数値を用いて考えてみましょう。
理解が難しい場合は、さらに多くの数値を試してみることが役立ちます。
このようなアプローチは、確率だけでなく数学の他の分野でも重要な考え方です。
解答を書きながら進める
数学が苦手な人の中には、「短い解答が良い」と考えて、公式を駆使してスマートに解答しようとする人がいます。
しかし、入試ではどのように解答しても、正解なものは「正解」と評価されます。
たとえば、私であれば、数学の問題を解く際には、「全てを書き出せば答えにたどり着けるか」という観点を持っています。
俗に力業とか、ガチンコといった呼び方をしています。
必要ならば、樹形図を描くことをためらわず、このような「書き出す」習慣を身に付けることで、得点を安定させることができます。
また、人間は「書き出す」ことで頭の中を整理することができるので、曖昧だった問題の理解もクリアーになることも珍しくありません。
確率を得意分野に変える勉強方法
最後に、確率を得意とするための勉強法について説明します。
具体的に何を、どんなことをしたらいいのか、あげていきます。
演習量を増やす
先に述べたように、確率に関しては演習量を増やすことが重要です。
例えば「ハッとめざめる確率」といった、確率に特化した参考書を使ってみるのがいいでしょう。
チャート式のような他の分野が入っているような問題集や参考書は、確率がわからない、確率ができない人には向いていません。
確率は数学の中でも、少し異種の分野で、確率を解く上での考え方を理解することが必要です。
「ハッとめざめる確率」は、公式を暗記するのではなく、場合の数や確率を扱う際の「ものの数え方」「具体的な考え方」に焦点を当てていて、数学全般のスキルの向上とともに、確率を得意とするための非常に有効な手段ですよ。
日常的に図を描き、手を動かす
また、日頃から図やグラフを描くこと、手を動かして数学を学ぶ習慣を身に付けることは非常に重要です。
この習慣は確率に限らず、数学の全分野において役立ちます。
多くの生徒を指導している経験から確実に言えるのは、数学ができない生徒ほど、図やグラフを書かないし、書けないのです。
逆に、数学を得意とする人、数学ができる人というのは、図やグラフを書くなり、イメージするなりして解いているのです。
2025年共通テストから確率はほぼ必須で逃げられない
繰り返しになりますが、確率がわからない、確率ができないという高校生、本当に多いんです。
数学の他の分野では点数が取れるのに、確率はダメ‥という人も珍しくありません。
ここのポイントは「点数が取れる」であって、「数学が得意」とは言っていないところです。
学校の定期試験で「点数が取れる」という生徒のほとんどは、公式を覚えている、やり方を覚えているというケースです。
評定がいいのに、模試ができない…と同じ原理ですね。
確率にいたっては問題がかわるとできないという生徒が山ほどいます。
そういった意味でも、確率がわからない、確率ができないという高校生の実態は想像以上に多いんです。
2024年の共通テストまでは、確率が嫌!というのなら、確率を避けて受験することもできました。
しかし、2025年以降の共通テストはいよいよ確率を避けることができなくなりました。
実際に、2月の新規依頼の高校生、ほぼ確率対策という、前代未聞な事態が起きています。
というのも、数学B「統計的な推測」が定期試験に入ってしまって、わからない…という生徒がたくさんいます。
数学B「統計的な推測」がわからないというより、確率が出せない…という生徒がたくさんいました。
確率ができなくて、国公立が狙えない…ということにならないように、早めに対策をうちましょう。
まとめ
確率がわからない、確率ができないという問題は、多くの人が特定の行動パターンから生じているケースも珍しくありません。
まずは、今回紹介した、確率がわからない、確率ができない原因から該当するものをみつけてみましょう。
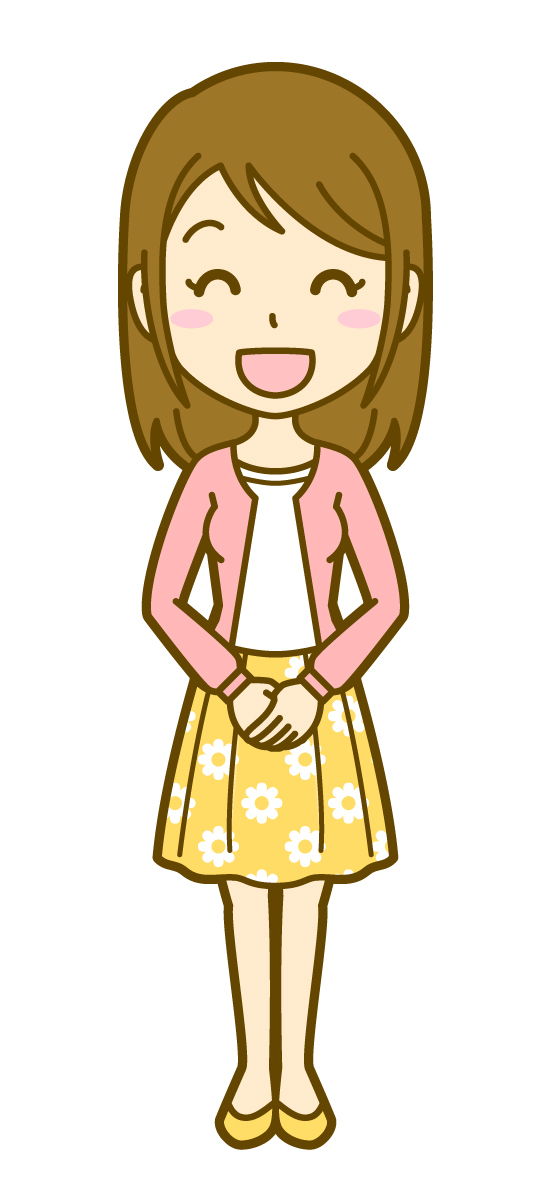
2025年の共通テストから確率はほぼ必須確定です。確率がわからなすぎ、確率ができなさすぎでどうしたらいいのかわからないのなら、マンツーマンでやり方を教えてもらうのがベストです。でも、いきなり家庭教師をつけることや、マンツーマン塾に入塾するのは塾代も高額なので失敗したら…と思うと不安かもしれません。まずはオンラインのマンツーマン無料体験指導を受けて、あなたに合った対策を教えてもらう方法もあります。今なら完全無料で体験授業を受けられますよ。